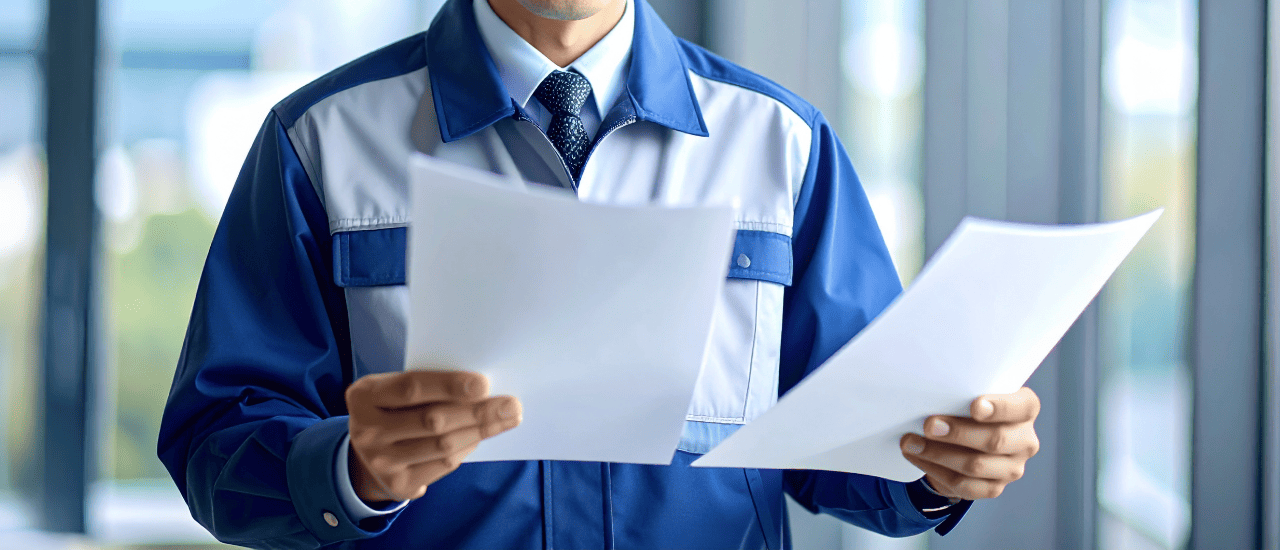アスベスト事前調査の流れを7ステップで解説|義務化された内容とは

「アスベストの事前調査が義務化されたのは知っているが、具体的に何から手をつければいいのか分からない」
「調査から行政への報告まで、全体の流れを正確に把握したい」
2022年の法改正以降、すべての解体・改修工事で原則必須となったアスベスト事前調査。事業者の皆様にとって、コンプライアンス上、極めて重要な業務ですが、そのプロセスが複雑で分かりにくいと感じている方も多いのではないでしょうか。
調査の段取りを間違えたり、報告を忘れたりすると、罰則の対象となるだけでなく、工事の遅延や企業の信頼失墜にも繋がりかねません。
そこで本記事では、アスベスト分析の専門家として、事前調査の全体像を明確にするため、計画段階から完了までの一連の流れを「7つの具体的なステップ」に分けて分かりやすく解説します。この記事を読めば、調査会社とのやり取りや、工事全体の進捗をスムーズに管理できるようになります。
目次
まずは前提知識:アスベスト事前調査が「義務」である理由
具体的な流れに入る前に、なぜこの調査が法律で厳格に義務付けられているのかを簡単におさらいしましょう。理由は大きく3つあり、それぞれが作業員、周辺住民、そして事業そのものを守るためです。
- 作業員の安全確保(労働安全衛生法): 飛散したアスベストから作業員の健康を守ります。
- 周辺環境の保全(大気汚染防止法): 現場周辺へのアスベスト飛散を防ぎ、地域住民を守ります。
- 事業リスクの回避: 工事の中断や予期せぬ費用の発生、行政処分といった経営リスクを避けます。
事前調査は、これらのリスクを回避し、安全な工事を実現するための第一歩なのです。
【完全ガイド】事前調査の具体的な7ステップ

それでは、計画から完了までの具体的な流れを7つのステップで見ていきましょう。アスベスト分析の専門家として、各ステップの要点を解説します。
ステップ1調査の計画と有資格者の選定
すべての始まりは、適切な調査計画と、信頼できる専門家の選定です。事前調査は誰でも行えるわけではなく、「建築物石綿含有建材調査者」という国の定めた資格を持つ者でなければ実施できません。まず、工事の発注者は、こうした有資格者が在籍する調査会社などに相談し、建物の規模や工事内容を伝えて調査計画を立てる必要があります。
ステップ2図面調査(文献調査)の実施
選定された調査者は、まず机上での調査を行います。施主(発注者)から提供された設計図書、仕様書、竣工年などの資料を精査し、アスベスト含有の可能性がある建材がどの部分に使用されているかの「あたり」をつけます。この段階で、明らかにアスベストが使われていない建材や、逆に使用されている可能性が極めて高い建材をリストアップします。
ステップ3現地での目視調査
次に、調査者が実際に現地に赴き、図面調査の結果と現場の状況を照らし合わせながら、建材の状態を目で見て確認します。壁や天井、床、屋根、断熱材など、図面だけでは分からない部分や、過去のリフォームで変更された箇所などを、経験と知識に基づいて丹念に調査し、写真等で記録を残します。
ステップ4分析調査のための検体採取と分析依頼
図面調査や目視調査でアスベスト含有の有無が判断できない「不明な建材」があった場合、このステップに進みます。調査者は、その建材の一部を、周囲に飛散させないよう慎重に採取(サンプリング)し、弊社のような専門の分析機関で分析することになります。ここで初めて、科学的根拠に基づきアスベストの有無が確定します。この分析調査こそが、調査全体の心臓部と言える最も重要な工程です。
ステップ5調査結果報告書の作成
すべての調査(図面、目視、必要であれば分析)が完了したら、調査会社はその結果をまとめた「事前調査結果報告書」を作成します。この報告書には、調査を行った建物の概要、調査者の氏名、各建材のアスベスト含有の有無、分析結果などが法的に定められた様式で記載されます。この書類は、後の行政報告や現場での記録として非常に重要になります。
ステップ6行政への電子報告(G-Biz IDを利用)
一定規模以上(解体工事は80㎡以上、改修工事は請負金額100万円以上)の工事では、作成された報告書の内容を、国が管轄する「石綿事前調査結果報告システム」を通じて、労働基準監督署および自治体へ電子報告することが義務付けられています。報告には、法人・個人事業主向けの共通認証システムである「G-Biz ID」のアカウントが必要となります。
ステップ7調査結果の掲示と書類の保管
最後に、工事現場における義務です。事前調査の結果(アスベストの有無など)を記載したA3サイズ以上の掲示物を、工事現場の見やすい場所に設置しなければなりません。また、作成した事前調査報告書は、工事終了後も3年間保管する義務があります。
事前調査で「アスベスト有り」と判明した場合の流れ
もしステップ4の分析調査などでアスベストの含有が判明した場合、事業者は飛散防止措置を講じる義務が生じます。具体的には、アスベストのレベルに応じた「作業計画書」を作成し、労働基準監督署へ届け出た上で、隔離や湿潤化といった厳格なルールに則って除去工事などを進めることになります。
事前調査の7ステップを理解し、安全な工事計画を
アスベスト事前調査は、以下の7つのステップで進められる、計画的かつ法的に厳格なプロセスです。
- ステップ1:計画と有資格者の選定
- ステップ2:図面調査
- ステップ3:目視調査
- ステップ4:分析調査(最も重要)
- ステップ5:報告書の作成
- ステップ6:行政への電子報告
- ステップ7:結果の掲示と保管
これらの流れを正確に理解し、一つ一つのステップを確実に実行することが、法令遵守はもちろん、あらゆるリスクから関係者を守ることに繋がります。
HAKUTOアスベスト分析センターは、事前調査のプロセス全体に関するご相談やアドバイスも承っております。そして、調査の根幹をなす「分析」においては、迅速かつ高精度な結果をご提供し、お客様の安全な工事計画を強力にバックアップいたします。分析調査が必要になった際は、ぜひ一度お問い合わせください。
アスベストの定性分析が必要な時は、当社にご相談ください。
お客様の状況に合わせた最適なご提案をさせていただきます。