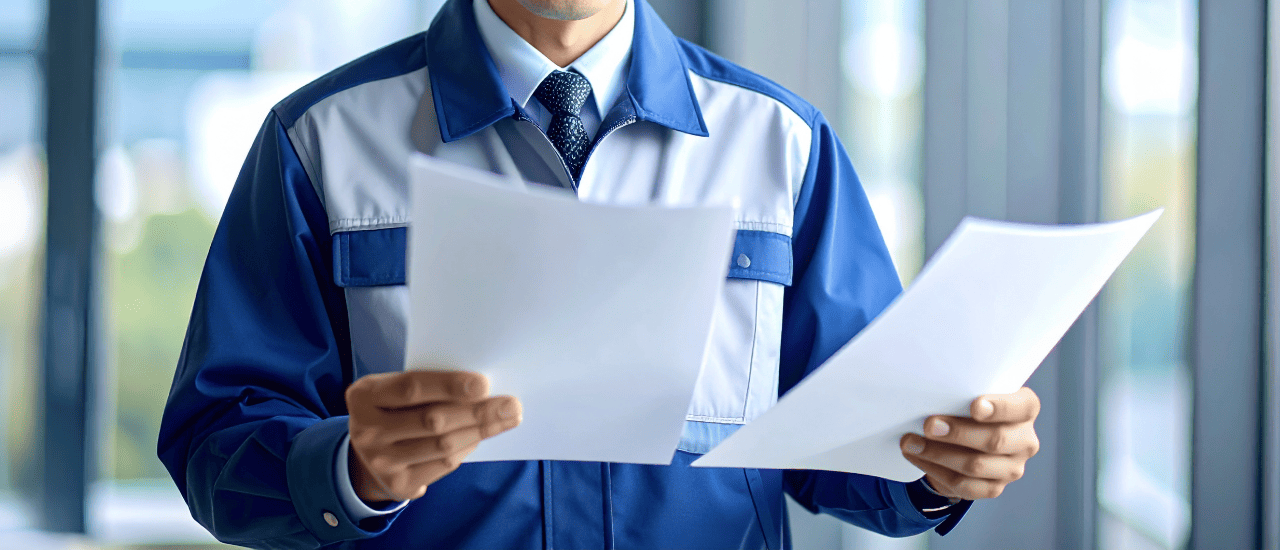石綿とアスベストの違いとは?同じものを指す言葉の語源や定義を解説

建物の解体やリフォームを検討する中で、アスベストに関する情報を集めていると、様々な言葉を目にすることでしょう。
「アスベスト」というカタカナ表記もあれば、「石綿」という漢字表記もある。さらに、「石綿」は「いしわた」と読まれたり、「せきめん」と読まれたりもします。
「これらは全部違うものなのだろうか?」「危険性に何か差があるのでは?」
こうした用語の混乱は、アスベスト問題の理解を妨げる最初の壁となり、多くの方を不安にさせています。
ご安心ください。この記事で、その疑問をきっぱりと解消いたします。結論から申し上げると、これらはすべて「同じもの」を指す言葉です。
この記事では、アスベスト分析の専門家である私たちHAKUTOが、なぜ複数の呼び方が存在するのか、その語源や法律上の定義、読み方の違いによるニュアンスまで、基本のキから徹底的に解説します。
この記事でわかること
- アスベストと石綿(いしわた・せきめん)が同じものであることがわかる
- なぜ複数の呼び名や読み方が存在するのか、その理由がわかる
- 法律や専門分野でどの言葉が使われるかがわかる
- 用語に惑わされず、正確な情報収集ができるようになる
この記事を読み終える頃には、用語の混乱という霧が晴れ、アスベスト問題への理解がより一層深まっているはずです。
目次
結論:アスベストと石綿(いしわた・せきめん)は全く同じもの
まず、最も重要な結論からお伝えします。
「アスベスト」と「石綿(いしわた、せきめん)」は、呼び方が違うだけで、指し示している物質は全く同じです。
どちらの言葉も、蛇紋石(じゃもんせき)族および角閃石(かくせんせき)族に属する、天然に産する繊維状の鉱物群を総称したものです。具体的には、クリソタイル、アモサイト、クロシドライトなど6種類の繊維状鉱物を指します。
では、なぜ同じものに複数の呼び名があるのでしょうか。その理由は、言葉の由来と使われる場面の違いにあります。
- アスベスト(asbestos): 英語由来の言葉
- 石綿(いしわた、せきめん): 日本語の言葉
非常にシンプルですが、これがすべての基本です。「アスベスト=石綿」と覚えていただければ、情報の混乱は格段に少なくなるでしょう。
なぜ複数の呼び方が存在するのか?語源と読み方の違い

同じものを指すのになぜ呼び方が違うのか、もう少し深掘りして解説します。言葉の背景を知ることで、より理解が明確になります。
「アスベスト」の語源
「アスベスト」は、英語の “asbestos” に由来します。この言葉はさらに、ギリシャ語の “asbestos(アスベストス)” に遡ります。これは「消すことができない」「不滅の」といった意味を持つ言葉で、アスベストの優れた耐火性・耐久性という特性を的確に表しています。
日本では、この英語由来のカタカナ表記が、ニュースや一般社会で最も広く浸透している呼び方と言えるでしょう。
「石綿」の語源と2つの読み方
一方、「石綿」は日本語の名称です。その見た目が綿(わた)のようであることから、「石の綿」すなわち「石綿(いしわた)」と呼ばれるようになりました。非常に分かりやすいネーミングです。
この「石綿」には、2つの読み方が存在します。
1. 「いしわた」という読み方(訓読み)
こちらは、古くから使われている日本語の伝統的な読み方(大和言葉)です。「石の綿」という言葉の成り立ちをそのまま読んでおり、一般の方にも馴染みやすい響きかもしれません。
2. 「せきめん」という読み方(音読み)
こちらは、漢字の音を読んだもので、主に学術的な場面や、法律、行政の文書などで専門用語として用いられる読み方です。後述しますが、日本の法律では「石綿」はすべて「せきめん」と読まれます。
厚生労働省も、法令などでは「せきめん」と読むことを公式に示しており、専門家や行政関係者の間では「せきめん」が標準的な読み方として定着しています。
法律や公的文書での使われ方
アスベストと石綿の使われ方は、場面によって明確な傾向があります。
法律・行政文書では「石綿(せきめん)」が統一名称
アスベストに関する最も重要な法律である「石綿障害予防規則」は、「せきめんしょうがいよぼうきそく」と読みます。また、「大気汚染防止法」などの関連法規においても、アスベストを指す言葉はすべて「石綿(せきめん)」で統一されています。
このように、公的な文書や専門的な文脈では、「石綿(せきめん)」が正式名称として使われるのがルールです。
ニュースや一般会話では「アスベスト」が主流
一方で、テレビのニュースや新聞、一般的な会話では、「アスベスト」という言葉が圧倒的に多く使われます。これは、社会問題として広く認知された際に、カタカナ表記の「アスベスト」が主に使われたため、国民にとって最も馴染み深い言葉となったからです。
「石綿」と聞いたら「アスベスト」と変換して大丈夫
ここまで解説してきたように、呼び方や読み方が複数あっても、指し示す物質の危険性に何ら変わりはありません。
- 業者から「せきめんの調査が必要です」と言われた。
- 古い図面に「いしわた保温筒」という記載があった。
- ニュースで「アスベスト問題」について報道している。
これらはすべて、同じ有害物質「アスベスト」に関する話です。「いしわた」だから危険性が低い、「せきめん」は特殊なもの、といった誤解は絶対にしないでください。どの言葉が出てきても、ご自身の頭の中では「アスベスト」という言葉に変換し、同じレベルの警戒と適切な対応が必要だと認識することが重要です。
よくある質問(FAQ)
Q1. 呼び方によって、指しているアスベストの種類に違いはありますか?
A1. いいえ、ありません。「アスベスト」も「石綿」も、クリソタイル(白石綿)、アモサイト(茶石綿)、クロシドライト(青石綿)など、法律で規制されている6種類すべての繊維状鉱物を包含する言葉です。
Q2. なぜ法律では「せきめん」という読みに統一されているのですか?
A2. 学術用語や法律用語では、言葉の意味を厳密に定義し、一貫性を持たせるために、漢語由来の音読みが好まれる傾向があります。これにより、解釈のブレを防いでいると考えられます。
Q3. 業者と話すときは、どの言葉を使えば良いですか?
A3. どちらを使っていただいても問題なく通じます。一般的には「アスベスト」が最も広く使われており、スムーズに話が進むでしょう。もし「せきめん」という言葉を使えば、「この人はよく勉強しているな」と専門家から一目置かれるかもしれません。
まとめ:言葉の違いに惑わされず、本質を正しく理解しよう
今回は、混同しやすいアスベストと石綿という言葉の違いについて解説いたしました。
- まとめのポイント1:「アスベスト」と「石綿(いしわた・せきめん)」は、英語由来か日本語由来かの違いだけで、指し示す物質は全く同じです。
- まとめのポイント2:「石綿」には、昔ながらの「いしわた(訓読み)」と、法律や専門分野で使われる「せきめん(音読み)」の2つの読み方が存在します。
- まとめのポイント3:どの呼び方であっても、物質の危険性に差はありません。言葉の違いに惑わされず、「アスベスト=危険な鉱物」という本質を正しく理解することが、安全対策の第一歩です。
用語の壁を乗り越え、アスベストに関する正しい知識を身につけることは、ご自身や大切な人々を健康被害から守る上で極めて重要です。
もし、ご自宅や管理されている建物でアスベストの有無が疑われる場合は、言葉の違いに悩む前に、ぜひ一度私たちのような専門家にご相談ください。科学的な分析を通じて、皆様の疑問や不安に明確な答えをお示しします。
アスベストの定性分析が必要な時は、当社にご相談ください。
お客様の状況に合わせた最適なご提案をさせていただきます。