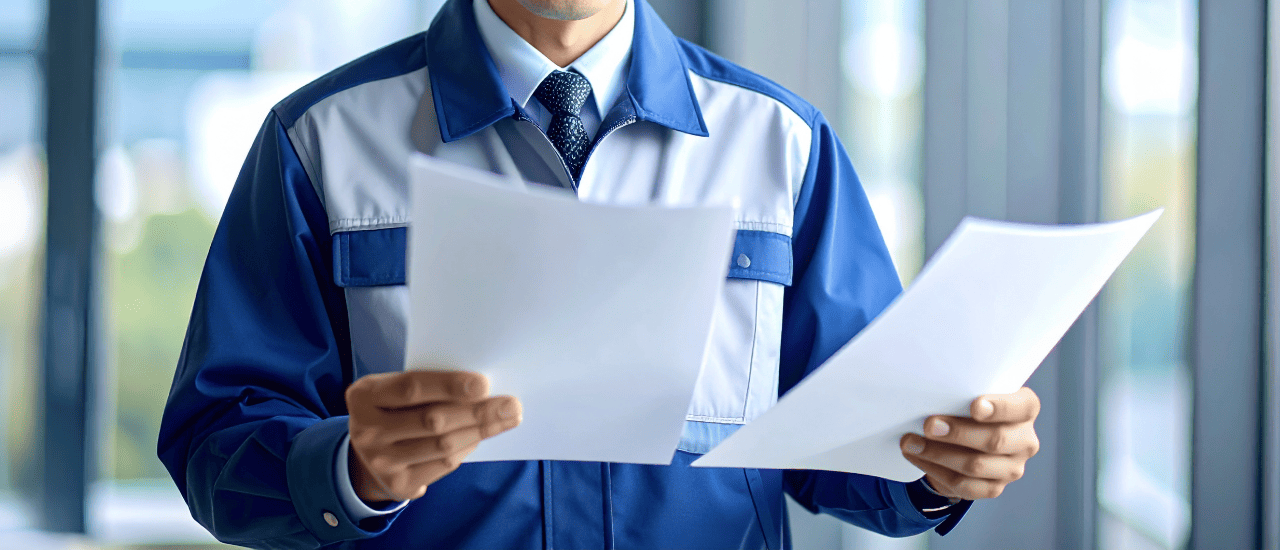アスベストの定性・定量分析、どっちを選ぶ?費用と必要性をケース別に徹底比較

アスベスト分析を依頼しようと検討する中で、「定性分析」と「定量分析」という2つの言葉を目にすることがあります。この2つは、アスベスト分析における主要な手法ですが、その目的と役割は全く異なります。
「自分の場合は、どちらの分析を依頼すれば良いのだろう?」
「費用が違うみたいだけど、何が基準になるの?」
適切な分析方法の選択は、法令遵守はもちろん、無駄なコストをかけないためにも非常に重要です。もし誤った選択をすれば、余計な費用が発生したり、法的に必要な情報が得られなかったりする可能性もあります。
本記事では、アスベスト分析の専門家として、この「定性分析」と「定量分析」の根本的な違いから、具体的なケースごとの適切な選び方まで、分かりやすく徹底的に比較・解説します。
まずは基本の確認「定性分析」と「定量分析」の役割
比較に入る前に、まずはそれぞれの分析が「何を知るためのものか」という基本的な役割を理解しましょう。
定性分析アスベストの「有無」を調べる分析
定性分析の目的はただ一つ、「その建材に、アスベストが含まれているか、いないか(有無)」を明らかにすることです。
いわば、「Yes / No」を判定する検査です。
この分析により、もしアスベストが含まれていた場合は、それが6種類あるアスベストのうちどの種類(クリソタイル、アモサイトなど)なのかも特定できます。法律で定められた事前調査において、まず基本となるのがこの定性分析です。
(JIS規格では「JIS A 1481-1」がこれに該当します)
定量分析アスベストの「含有率」を調べる分析
一方、定量分析の目的は、定性分析で「有り」と判定された建材に対し、「アスベストが、具体的に何パーセント含まれているか(含有率)」を数値で明らかにすることです。
こちらは、具体的なスコアを出す検査とイメージしてください。
結果は、「アスベスト含有率 〇.〇%」というように、建材全体の重さに対する割合(質量分率)で示されます。
(JIS規格では「JIS A 1481-2」などがこれに該当します)
重要なのは、定量分析は、定性分析で「有り」と判明した検体に対して、さらに詳細な情報を得るために行う、次のステップの分析であるという点です。
ケース別あなたの場合はどっちが必要?徹底比較

それでは、本題である「どちらの分析を選ぶべきか」を、具体的な4つのケースに分けて見ていきましょう。
ケース1一般的な解体・リフォーム工事の事前調査の場合
結論 → 原則として「定性分析」だけで十分です。
解説
建築物の解体やリフォームを行う際、法律(石綿障害予防規則)で求められるのは、まず「アスベストの有無」を把握し、それに応じた安全対策を講じることです。
定性分析で「アスベスト有り」という結果が出た時点で、その建材は法律上の「石綿含有建材」として扱われ、含有率が0.2%であれ50%であれ、同様の飛散防止対策や除去措置が義務付けられます。
そのため、ほとんどの工事では、まず定性分析で有無を確認し、「有り」と出た場合はその結果をもって対策計画を立てるのが、最も効率的でコストを抑えられる一般的な進め方です。高価な定量分析まで行い、正確な含有率を調べる必要性は低いと言えます。
ケース2アスベスト含有廃棄物の処理方法を判断したい場合
結論 → 「定量分析」が必要です。
解説
アスベスト分析の結果が最も重要になる局面の一つが、廃棄物の処理です。
廃棄物処理法では、アスベスト含有率が0.1%を超える廃棄物は、通常の産業廃棄物とは異なる「特別管理産業廃棄物」に分類され、専門の処理施設で厳重に管理・処分することが義務付けられています。当然、処理費用も高額になります。
定性分析で「有り」と出ただけでは、この0.1%という基準を超えているかどうかは判断できません。
そのため、除去した建材を適正に処理するため、また、処理コストを正確に見積もるために、定量分析による正確な含有率の測定が不可欠となるのです。
ケース3「含有しているが、0.1%以下であること」を積極的に証明したい場合
結論 → 「定量分析」が必要です。
解説
これはケース2と関連しますが、より戦略的な活用法です。
例えば、定性分析で「アスベスト有り」と判定されたものの、建材の種類や製造年代から「含まれていても、ごく微量で0.1%以下なのではないか」と推測される場合があります。
このとき、もし定量分析を行って「含有率0.1%以下」であることを科学的に証明できれば、その建材は法的なアスベスト含有建材としての扱いから外れ、除去や廃棄物処理にかかるコストを大幅に削減できる可能性があります。
リスクと分析費用を天秤にかけ、コスト削減のメリットが大きいと判断される場合に、定量分析は非常に有効な手段となります。
ケース4公共工事や、発注者から特別な仕様書が出ている場合
結論 → 仕様書によりますが、「定量分析」が求められることが多いです。
解説
国や地方自治体が発注する公共工事や、一部の民間大手企業が発注する工事では、法律の最低基準よりも厳しい独自の安全基準を設けている場合があります。
その場合、工事の仕様書や契約書の中で、「アスベストが検出された場合は、定量分析まで実施し、含有率を報告すること」が条件として明記されていることがあります。
このようなケースでは、法律上の必要性とは別に、契約を履行するために定量分析が必須となります。必ず工事の仕様書を事前に確認しましょう。
費用と納期の比較
どちらの分析を選ぶかには、費用と納期も大きく関わってきます。
費用
定量分析は、定性分析よりも高度な測定技術と手間を要するため、一般的に費用は高額になります。
納期
同様に、分析にかかる時間も定量分析の方が長くなる傾向にあり、納期も長くなります。
この点からも、明確な目的がないまま安易に定量分析を依頼すると、不要なコストと時間のロスに繋がってしまうことが分かります。
最適な分析は「目的」によって決まります
「定性分析」と「定量分析」の違いと選び方について、ご理解いただけたでしょうか。
- 定性分析(JIS A 1481-1)
まず「有無」を知るための、全ての基本となる分析。 - 定量分析(JIS A 1481-2)
「有り」と分かった上で、「含有率」という具体的な数値が必要な場合に行う、詳細な分析。
結論として、「何のために分析結果が必要なのか?」という目的を明確にすることが、最適な分析方法を選ぶ上での最大のポイントです。
私たちHAKUTOアスベスト分析センターは、お客様からご依頼をいただく際に、必ずその目的や背景をお伺いします。そして、ただ分析を請け負うだけでなく、お客様の状況にとって、どの分析が最も適切でコスト効率が良いのかを、専門家の立場からご提案させていただきます。
どちらの分析が必要か迷われた際は、決して一人で悩まず、まずは私たちにご相談ください。
アスベストの定性分析が必要な時は、当社にご相談ください。
お客様の状況に合わせた最適なご提案をさせていただきます。