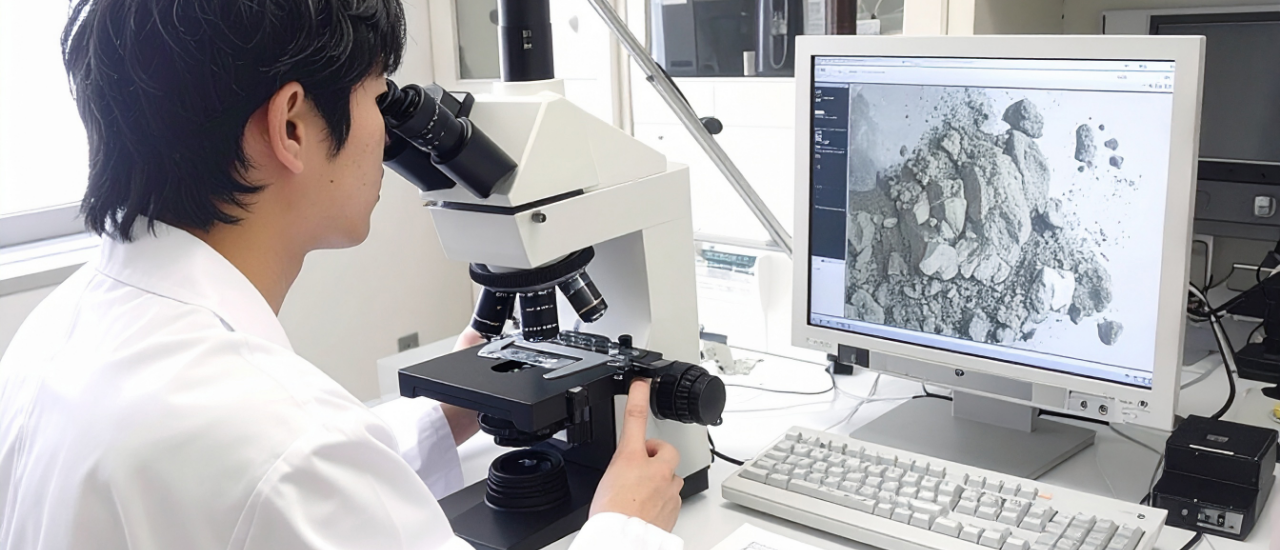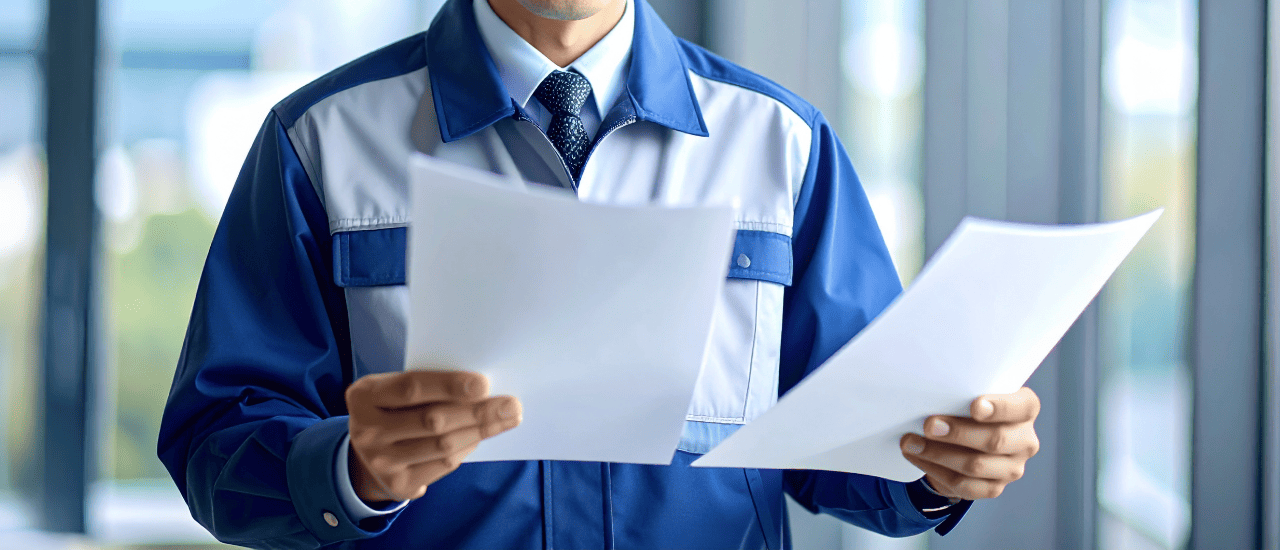【2025年最新版】アスベスト関連法律の改正点まとめ|罰則や事業者の義務を解説

「最近、アスベストの規制が厳しくなったと聞くけれど、具体的に何が変わったのだろう?」
「自社の事業は、新しい法律にきちんと対応できているだろうか?」
建設・不動産・解体といった業界に携わる事業者様であれば、このように感じている方も多いのではないでしょうか。ここ数年でアスベスト関連法規(特に石綿障害予防規則)は段階的に、そして大幅に改正・施行され、事業者が遵守すべき義務は大きく変わりました。
知らなかったでは済まされないこれらの規制は、違反した場合に厳しい罰則が科されるだけでなく、従業員や地域住民の健康を脅かすリスクに直結します。
本記事では、2025年の現時点で事業者が必ず押さえておくべきアスベスト関連法改正の重要ポイントを総まとめにし、「何をすべきか」を専門家の視点から分かりやすく解説します。
目次
なぜ法改正が続いたのか?その背景
まず、なぜこれほど規制が強化されたのか、その背景を理解することが重要です。
過去の規制にも関わらず、アスベスト含有建材の見落としや、規制対象外であった小規模な改修工事などでの対策が不十分であったために、アスベストばく露(アスベスト繊維を吸い込むこと)による健康被害が後を絶ちませんでした。
特に、リフォームや修繕といった比較的小規模な「改修工事」での対策の抜け漏れが問題視されていました。
こうした背景から、アスベストばく露のリスクを社会全体で根絶することを目的に、規制の対象範囲を広げ、事業者の責任をより明確にするための大規模な法改正が行われたのです。
最重要ポイント1事前調査の実施と報告の完全義務化
今回の法改正で最も影響が大きいのが、「事前調査」に関する義務の強化です。
何が変わったのか?
以前は一定規模以上の工事が対象でしたが、2022年4月1日から、請負金額や規模の大小に関わらず、建築物・工作物の全ての解体・改修工事で事前調査が義務となりました。これにより、例えば「壁に穴を一つ開ける」といったごく小規模な作業でも、法律上は事前調査の対象となります。
誰が調査できるのか?
さらに、2023年10月1日から、事前調査は「建築物石綿含有建材調査者」という専門の資格を持つ者でなければ実施できなくなりました(※例外規定あり)。これにより、調査の信頼性と専門性が担保されることになりました。
調査結果の報告義務
加えて、以下のいずれかに該当する工事では、アスベストの有無に関わらず、調査結果を「石綿事前調査結果報告システム」を通じて、労働基準監督署と地方自治体に電子報告することが義務付けられています。
- 解体部分の床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事
- 請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
- 請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体・改修工事
事業者がすべきこと
- 全ての解体・改修工事で、必ず有資格者による事前調査を実施する。
- 報告対象の工事では、必ず電子システムで報告を行う。
- 調査結果の記録を作成し、3年間保管する。
最重要ポイント2調査・分析対象の拡大
事前調査の対象となる建材の範囲も大きく拡大されました。
何が変わったのか?
これまでは見落とされがちだった建材も、明確に調査対象として規定されました。
- 塗料や仕上塗材
2022年4月以降、アスベストが含有されている可能性がある塗料(吹付け工法)なども調査が必須となりました。 - より広い範囲の建材
ネジで固定されているような建材でも、一体となっているものは全て調査対象です。例えば、外壁のサイディングとその目地のシーリング材なども、個別に調査する必要があります。

「分析」の重要性の高まり
この調査対象の拡大により、「図面や目視だけではアスベスト含有の有無を判断できないケース」が格段に増えました。
法律では、含有の有無が明らかでない場合は「含有しているものとみなす(みなし措置)」か、「検体を採取して分析を行う」ことによって、有無を確定させなければならないと定められています。
みなし措置は安全策ではありますが、本来は不要な高額の対策費用が発生する可能性があります。そのため、コストを適正化し、正確な対策計画を立てる上で、信頼できる機関による「アスベスト分析」の重要性がこれまで以上に高まっています。
事業者がすべきこと
- 「この建材は大丈夫だろう」という思い込みを捨てる。
- 図面や目視で判断できない建材については、積極的にアスベスト分析を依頼し、有無を科学的に証明する。
最重要ポイント3罰則の強化と作業記録の保管義務
法改正に伴い、義務違反に対する罰則も強化されています。
何が変わったのか?
事前調査の実施や報告義務の違反、除去作業における措置義務違反などに対して、直接的な罰則(懲役や罰金)が科される可能性が明確に示されています。
また、事前調査や実際の作業に関する記録(写真など)を作成し、工事終了後も3年間保管することが義務付けられました。これにより、後からでも適正に作業が行われたかをトレースできるようになっています。
事業者がすべきこと
- 法令遵守を徹底し、罰則のリスクを正しく認識する。
- 調査から作業完了までの各工程で、写真を含む詳細な記録を残し、適切に保管する体制を整える。
2025年に事業者が押さえるべきこと
複雑に見える法改正ですが、事業者が今すぐ対応すべきことは、以下のポイントに集約されます。
- 「全ての工事で事前調査が必須」と認識を改める。
- 調査は必ず「有資格者」に依頼する。
- 判断に迷う建材は「必ず分析」に出して白黒つける。
- 対象工事では、電子システムでの「報告」を忘れない。
- 調査と作業の「記録」を確実に作成・保管する。
これらの法規制を遵守するための、全てのプロセスの基礎となるのが、信頼できる「事前調査」と「アスベスト分析」です。
私たちHAKUTOアスベスト分析センターは、最新の法規制に精通した専門家として、お客様が法令を遵守し、安全に事業を進められるよう、その根幹となる「アスベスト分析」を高品質・低価格でご提供します。
法改正に関するご不明点や、自社の対応が十分かどうかのご相談も含め、まずはお気軽にお問い合わせください。
アスベストの定性分析が必要な時は、当社にご相談ください。
お客様の状況に合わせた最適なご提案をさせていただきます。