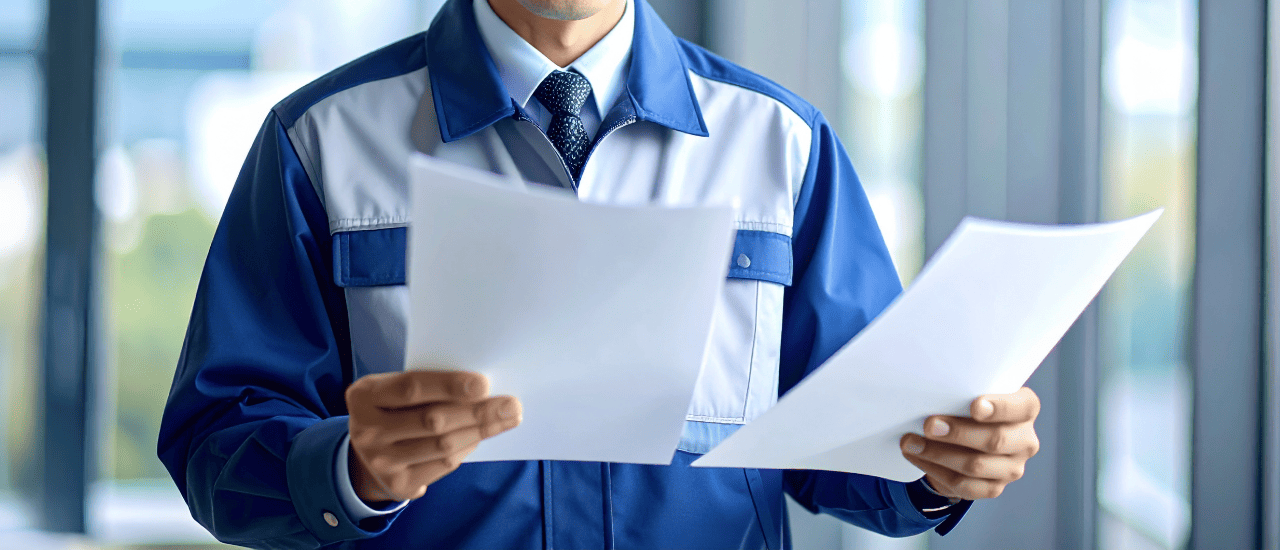アスベスト分析報告書が届いたら?「検出あり/なし」ケース別の対応フローと除去費用

「アスベスト分析を依頼し、手元に分析結果報告書が届いた。でも、この書類を元に、次に何をすれば良いのだろう?」
分析結果を受け取った多くの方が、このような疑問や、結果によっては不安を感じていらっしゃるかもしれません。特に「アスベスト検出(有り)」と記載されていた場合、どう行動すべきか分からず、戸惑ってしまうのも無理はありません。
本記事では、アスベスト分析の専門家として、分析結果が出た後に取るべき具体的なステップを、結果の内容別に分かりやすく解説します。この記事を最後までお読みいただくことで、ご自身の状況に合わせて次に何をすべきかが明確になり、落ち着いて適切な対応を進められるようになります。
まずは「分析結果報告書」の見方を理解しよう
対応を考える前に、まずは報告書に何が書かれているかを正しく理解することが重要です。書式は分析機関によって多少異なりますが、必ず記載されている中心的な項目は以下の2点です。
1アスベストの有無(定性分析結果)
最も重要なのがこの項目です。「検出されず(不検出)」と書かれているか、「〇〇を検出」と書かれているかを確認します。「〇〇」の部分には、クリソタイル、アモサイトといった検出されたアスベストの種類が記載されます。
2アスベストの含有率(定量分析結果)
定量分析まで依頼した場合に記載されます。「含有率 1.5%」のように、建材全体の重さに対するアスベストの割合が数値で示されます。この数値が0.1%を超えるかどうかが、法的な扱いの大きな分かれ目となります。
まずはご自身の報告書で、この「有無」と「含有率」がどうなっているかをご確認ください。
ケース別結果が出た後の具体的な対応フロー

分析結果が分かったら、次はいよいよ具体的なアクションに移ります。ここでは大きく2つのケースに分けて、対応フローを解説します。
ケースA分析結果が「アスベスト検出されず(不検出)」だった場合
まず、ご安心ください。分析に出した建材については、アスベストが含まれていないことが証明されたことになります。
取るべき行動
- 工事の計画通り進行
その建材についてはアスベスト対策が不要ですので、予定していた解体やリフォーム工事を計画通り進めることができます。 - 書類の保管
発行された分析結果報告書は、行った事前調査の記録として、他の関連書類と共に3年間保管する義務があります。工事が完了しても、すぐに廃棄しないようご注意ください。
注意点
忘れてはならないのが、「分析結果は、あくまで分析に提出した検体(サンプル)に対するもの」という点です。もし、他に調査が必要な建材が残っている場合は、それらについても別途、調査・分析が必要となります。建物全体の安全が確認されたわけではない、という点は心に留めておいてください。
ケースB分析結果が「アスベスト検出(有り)」だった場合
報告書に「検出」の文字があった場合、不安に感じるかもしれませんが、慌てる必要はありません。ここからは、法律に則って、安全かつ計画的に対策を進めていくフェーズに入ります。
ステップ1アスベストの「レベル」を把握する
まず重要なのが、検出されたアスベストがどの「レベル」に該当するかを把握することです。アスベスト建材は、飛散性の高さ(危険度の高さ)に応じてレベル1~3に分類され、レベルによって対策工事の方法や費用が大きく異なります。
- レベル1(最も危険)
吹付け石綿など。著しく発じん量が多く、厳重な隔離措置や届出が必要。 - レベル2(次に危険)
石綿含有保温材、耐火被覆材など。レベル1ほどではないが、飛散しやすいため高いレベルの対策が必要。 - レベル3(比較的危険度は低い)
石綿含有成形板(スレート屋根など)やPタイルなど。硬い素材のため通常は飛散しにくいが、破砕・切断時には飛散のリスクがある。
どのレベルに該当するかは、建材の種類によって決まります。分析結果と建材の種類を元に、工事を依頼する業者や専門家とレベルの認識を共有しましょう。
ステップ2専門家(施工業者など)と対策を協議する
アスベストが検出された場合、ここから先は専門家の知見が不可欠です。工事を依頼している元請業者や、アスベスト除去の専門業者に分析結果を提示し、今後の対策について協議を開始します。
ステップ3対策の方針を決定する
専門家との協議の上で、アスベストへの対策方針を決定します。主な方針は以下の通りです。
- 除去
最も根本的な解決策。アスベスト建材を完全に取り除きます。 - 封じ込め
薬剤を吹き付けるなどして、アスベストを固めて飛散しないようにする工法。 - 囲い込み
アスベスト建材を板材などで完全に覆い、室内環境と隔離する工法。
建物の状況や予算、今後の利用計画によって最適な工法は異なります。それぞれのメリット・デメリットを専門家からよく聞き、納得のいく方針を決定することが重要です。
ステップ4法的な手続きを進める
対策工事のレベルと工法が決まったら、法律に基づいた手続きを進めます。具体的には、以下のような対応が必要になります。
- 作業計画の作成
- 行政への届出
- 作業員の特別教育
- 適切な廃棄物処理
これらのステップは、基本的に元請業者や専門の除去業者が主体となって進めますが、発注者としても、こうした流れを理解しておくことが、円滑なプロジェクト進行の鍵となります。
信頼できるパートナー選びの重要性
ここまで見てきたように、アスベスト分析とその後の対応は、専門知識と法的な手続きが絡み合う複雑なプロセスです。
分析結果が「有り」だった場合も、「無し」だった場合も、その全てのプロセスの出発点となるのが、信頼性の高い「分析結果報告書」です。
私たちHAKUTOアスベスト分析センターは、お客様が安心して次のステップに進めるよう、JIS規格に準拠した精度の高い分析を、適正な価格でスピーディーにご提供しています。報告書の内容に関するご質問はもちろん、「この後どうすればいい?」といったご相談にも、専門家の立場からアドバイスさせていただきます。
分析結果は、安全な対策への第一歩
アスベストの分析結果が出た後の対応は、結果によって大きく異なります。
- 「検出されず」の場合
安心材料として、計画通り工事を進められます。ただし、報告書の保管と、他の建材の調査漏れがないかの確認が必要です。 - 「検出された」の場合
慌てずに、レベルの把握→専門家との協議→対策方針の決定→法的な手続き、というステップを一つずつ着実に進めていくことが重要です。
どちらのケースであっても、正確な分析結果がなければ、正しい第一歩を踏み出すことはできません。アスベストに関する不安や疑問は、確かな分析と専門家への相談で解消できます。分析後のご不明点も含め、いつでもお気軽にお問い合わせください。
アスベストの定性分析が必要な時は、当社にご相談ください。
お客様の状況に合わせた最適なご提案をさせていただきます。