アスベストの定性分析・定量分析(JIS A 1481)の違いとは?費用や選び方を専門家が比較解説
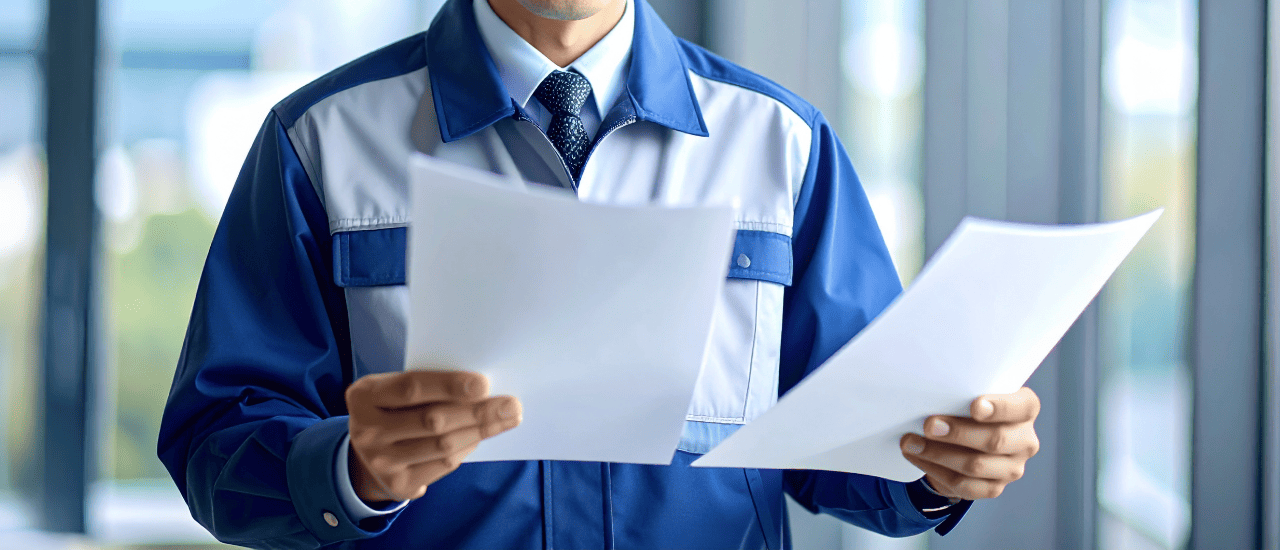
アスベスト分析を業者に依頼した際、見積書や報告書で「JIS A 1481-1」や「JIS A 1481-2」といった規格番号を目にしたことはないでしょうか。これらは日本産業規格(JIS)で定められたアスベストの公定分析法ですが、それぞれに明確な目的と役割の違いがあります。
「どちらの分析を依頼すれば良いのか分からない」「費用が違うけれど、何が異なるのだろう?」
こうした疑問は、アスベスト対策を適正かつ効率的に進める上で非常に重要です。
本記事では、アスベスト分析の専門家として、この2つのJIS規格の違いと、実務における適切な選び方を分かりやすく解説します。
目次
「あるか、ないか」を調べるJIS A 1481-1(定性分析)とは
まず基本となるのがJIS A 1481-1です。これは、調査対象の建材にアスベストが「含まれているか、いないか(有無)」を判定するための分析方法で、「定性分析」と呼ばれます。2022年4月から義務化された、建築物の解体・改修工事前に行う「事前調査」の結果、建材へのアスベスト含有が不明だった場合、この定性分析によって有無を明確にする必要があります。
分析方法と得られる結果
JIS A 1481-1では、主に以下の2つの手法を組み合わせて、高い精度でアスベストの有無を判定します。
- X線回折(XRD)分析
X線を試料に照射し、その結晶構造を分析することで、アスベスト特有のパターンを検出します。 - 位相差・分散顕微鏡法
顕微鏡を用いて、繊維の光学的な特性(色や屈折率の変化)を観察し、アスベスト繊維であることを直接目で見て確認します。
これらの分析の結果、報告書には「クリソタイルを検出」「アスベストは検出されませんでした」といった形で、アスベスト含有の有無と、検出された場合はその種類(クリソタイル、アモサイトなど6種類)が記載されます。
「どのくらいあるか」を調べるJIS A 1481-2(定量分析)とは
次にJIS A 1481-2は、JIS A 1481-1による定性分析でアスベストが「有り」と判定された建材に対し、それが「どのくらいの割合で含まれているか(含有率)」を測定するための分析方法です。こちらは「定量分析」と呼ばれます。
分析方法と得られる結果
JIS A 1481-2では、主にX線回折分析法を用いて、建材全体の重さに対してアスベストが何パーセント含まれているかを「質量分率(重量パーセント、wt%)」という単位で算出します。 この分析が重要となるのは、アスベスト含有率が0.1%を超えるかどうかが、法律上の大きな判断基準となるためです。例えば、アスベスト含有率が0.1%を超える廃棄物は、「特別管理産業廃棄物」として特別な方法で処理する必要があり、処理費用も大きく変わってきます。この0.1%という基準を明確に判断するために、定量分析が必要となるのです。
一覧表で比較JIS A 1481-1とJIS A 1481-2の主な違い
ここまでの内容を、分かりやすく一覧表にまとめました。| 項目 | JIS A 1481-1 (定性分析) |
JIS A 1481-2 (定量分析) |
|---|---|---|
| 目的 | アスベストの有無を調べる | アスベストの含有率(量)を調べる |
| 得られる結果 | 「〇〇を検出」「検出されず」など | 「含有率 〇.〇 %」など |
| 法的・実務上の役割 | 事前調査の基本となる分析 | 含有率0.1%超の判断、廃棄物区分の判断など |
| 費用感(当社比) | (基準) | やや高め |
| 納期感(当社比) | (基準) | やや長め |
実務における分析方法の選び方・使い分け
では、実際の現場ではどのように使い分ければ良いのでしょうか。

通常の解体・改修工事でまず必要なのは「JIS A 1481-1」
建築物の解体や改修工事を行う際、法律で求められているのは、まず「アスベスト含有の有無」を明確にすることです。そのため、通常、まず必要となるのはJIS A 1481-1による定性分析です。
定性分析の結果、アスベストが「有り」と判定されれば、その時点で「アスベスト含有建材」として法律に則った適切な措置(除去工事など)を行う必要があります。含有率が0.2%でも50%でも、法律上の扱いは同じ「アスベスト含有建材」となるため、多くの場合、高価な定量分析まで行わずに、定性分析の結果をもって対策を進めるのが一般的です。
JIS A 1481-2(定量分析)が必要となるケース
一方、定量分析が必要となるのは、以下のような限定的なケースです。
- 廃棄物処理のため、含有率0.1%超か否かを明確にしたい場合
- 「含有しているが、0.1%以下である」ことを証明し、規制対象外であることを示したい場合
- 公共工事や発注者の仕様書で、定量分析までの実施が明確に求められている場合
このように、定量分析は「含有率」という具体的な数値データがどうしても必要な場合に選択される、より詳細な分析と言えます。
要注意特に分析が重要な建材ケーススタディ
アスベスト含有の可能性がある建材は多岐にわたりますが、中でも特に分析の際に注意が必要な建材がいくつか存在します。ここでは代表的な3つのケースをご紹介します。

ケース1仕上塗材(リシン、スタッコ、タイルなど)
外壁や内壁の仕上げに使われる「仕上塗材」は、アスベスト含有の判断が特に難しい建材の一つです。1970年代から2000年代初頭まで広く使用され、意匠性を高めるためにアスベストが添加されていることがあります。
- 注意点
複数の層(下地調整材、主材、トップコートなど)で構成されており、どの層にアスベストが含まれているか分かりにくいのが特徴です。表面を少し削っただけの検体では、アスベストが含まれている下地層を見逃してしまう可能性があります。 - 推奨される対応
検体を採取する際は、必ず下地まで含めた全ての層を採取することが重要です。これにより、JIS A 1481-1の定性分析で正確な含有の有無を判定できます。
ケース2Pタイル・長尺シートなどの床材
事務所や店舗、学校などでよく見かけるPタイルや塩ビ系の長尺シートも、注意が必要な建材です。
- 注意点
アスベストは、タイルやシート本体ではなく、床に貼り付けるための接着剤に含まれているケースが非常に多く見られます。床材本体のみを分析して「アスベスト無し」と判断しても、接着剤に含有していれば法的な規制対象となります。 - 推奨される対応
床材を剥がした際に、下地に黒い接着剤が残っていないか確認してください。分析を依頼する際は、床材そのものと、下地の接着剤の両方を検体として提出することが最も確実です。
ケース3吹付け材(石綿含有吹付け材)
駐車場や機械室の天井、鉄骨の耐火被覆として使われる綿状の「吹付け材」は、最も飛散性が高く危険なレベル1建材に分類されます。
- 注意点
アスベストは、タイルやシート本体ではなく、床に貼り付けるための接着剤に含まれているケースが非常に多く見られます。床材本体のみを分析して「アスベスト無し」と判断しても、接着剤に含有していれば法的な規制対象となります。 - 推奨される対応
床材を剥がした際に、下地に黒い接着剤が残っていないか確認してください。分析を依頼する際は、床材そのものと、下地の接着剤の両方を検体として提出することが最も確実です。
信頼性の高い「定性分析」で、まず確実な一歩を
ここまで解説してきた通り、アスベスト分析には「有無」を調べる定性分析と、「含有率」を調べる定量分析があり、それぞれに明確な役割があります。
法律で定められた事前調査において、まず求められるのはJIS A 1481-1に基づく「定性分析」です。この分析によってアスベストの有無が判明すれば、法に則った適切な対策を進めることができます。多くの場合、お客様の「アスベストが含まれているか知りたい」という目的は、この定性分析で達成されます。
ハクトーアスベスト分析センターは、この最も重要で基本的な「定性分析」を、高品質かつ迅速にご提供することに特化しております。
定量分析は、廃棄物処理の区分けなど、特殊なケースで必要となる場合がありますが、まずは信頼性の高い定性分析で、対策の確実な第一歩を踏み出すことが重要です。アスベストの有無を明確にしたいとお考えでしたら、ぜひ当社にご相談ください。
アスベストの定性分析が必要な時は、当社にご相談ください。
お客様の状況に合わせた最適なご提案をさせていただきます。











